
ぼくはおばあちゃんが大好きだった。
ボケてるんだかボケてないんだかわからないぐらい天然で、家族親戚みんなを笑わせて、明るくする。
ぼくも、父も、血の繋がってない母も、親戚も。
みんな祖母のことが大好きだった。
そんなばーちゃんが突然亡くなったのは5年前のちょうど今ぐらい。
ぼくがたまたま帰省してた時、父と一緒に山菜取りにいった山の中で急に倒れたらしい。
そしてヘリコプターで病院に運ばれた。
その時、まさかばーちゃんが死ぬとは思わなかった。
ばーちゃんはもともと身体が悪く、20代の頃に医者から「あと半年で亡くなります」と宣言されたらしい。
それでも生き続け、何度か倒れて運ばれたりしながらも、おばあちゃんは生きつづけた。だから今回もきっと大丈夫なんだろうな、と思っていた。
だけどその翌日、おばあちゃんは、この世を去った。
延命処置することもできたけど、生前に「死ぬなら楽に死にたいな」と父に言っていたみたいで、その希望をかなえた。
父は苦渋の選択だったと思う。
亡くなった当日の夜、死んだばーちゃんが家に運ばれてきた。
顔にはタオルがかけられていて肌の色は色黒くなっていた。
部屋の真ん中にばーちゃんが仰向けになり、それを囲むように親戚家族みんなで大泣きした。ぼくももちろん大泣きした。父が泣くのも生まれて初めて見た。
だけど少し経つとその場が思い出話にかわった。おばあちゃんの天然エピソードをみんなで話し、そして笑い声までおきるようになった。
生きてようが死んでようがおばあちゃんはかわらず家族みんなを明るくさせて、あらためていい人だったんだな、と思った。
深夜、みんなが寝しずまったころ、ひとりでばーちゃんがいる部屋にいった。いるといってもそこには身体しかなく、命はもうない。
でも、今日がおばあちゃんと過ごせる最後の夜だと思った。
だから、おばあちゃんのいる部屋で過ごすことにした。
おばあちゃんに触ってみるとやっぱり冷たかった。だけど、やっぱりばーちゃんはばーちゃんだった。
死んで冷たくなったおばあちゃんの横で一緒に布団をかけて寝ることにした。
ばーちゃんはすごく冷たかった。
死んだ人間が冷たくなるのはなんとなく知ってた。
だけど、それでもあまりの冷たさにびっくりした。
魂が抜けた人間はこんなふうになるんだと思った。
ドラマみたいなことが起こるんじゃないかと声をかけてみるも、やっぱりなにも返事は返ってこない。
手を握ってもビクともしない。
腕を持ち上げてみても重くてあまり持ちあがらない。
おばあちゃんは天井のほうに顔をむけてずっと静止してる。
同じ布団の中から冷気がすごく伝わる。まるでドライアイスのように。
そんな、魂が抜け落ちて冷たくなったおばあちゃんと一緒に寝ていたら
なんだか「自分は生きている」と思った。
自分の手が温かいこと、重いはずの腕や足が自分の思い通りに動くこと、そしてそうやってなにかを感じることができること。
死んで冷たくなったばーちゃんの横で、ぼくはそんなことを思った。
いまぐらいの季節。
毎年このぐらいの時期になるとおばあちゃんのことを思い出す。
そして、死んだおばあちゃんと一緒に寝た夜のことがよみがえる。
その感覚を思い出すたび、
手のひらをぎゅーっとにぎって、自分の手が温かいことを確認たび、
「自分は生きてる」ということを実感する。

ばーちゃんは最後にそんなことを教えてくれた。










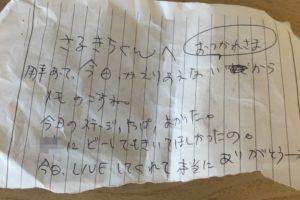
コメントを残す